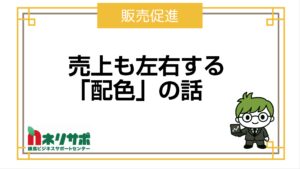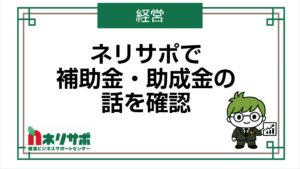フリーランス法で何が変わる?
2024年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下、フリーランス法)が施行されました。
働き方の多様化の中、フリーランスという働き方もまたその選択肢の一つとなってきています。選択肢が増える一方で、発注事業者・フリーランス間でのトラブルが顕在化してきており、課題を解決する必要が出てきました。
これらを背景に、フリーランスが安心して働ける環境整備を目指して、このフリーランス法は制定されました。
<フリーランス法の対象となる事業者>
フリーランス法では、原則として、対等な立場になりにくい"個人”と"組織”間での関係に着目しています。
このことから従業員を使用する発注事業者を「特定業務委託事業者」、従業員を使用しないフリーランスを「特定受託事業者」と定義し、整備されています。
したがって消費者個人はもちろんフリーランスからの会社への発注も対象となりません。
ただし、業務委託をする事業者についても、上記の「特定業務委託事業者」のほかに従業員の有無を問わない「業務委託事業者」も規定されており、取引条件の明示義務など発注事業者がフリーランスである場合にも対象となるものがありますので注意が必要です。
<フリーランス法における義務および禁止行為など>
フリーランス法では、以下のように『取引の適正化』と『就業環境の整備』に区分し、計7つの義務が定められています。
【取引の適正化】
- 取引条件の明示
- 期日における報酬支払
- 発注事業者の7つの禁止行為
【就業環境の整備】
- 募集情報の的確表示
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮
- ハラスメント対策に係る体制整備
- 中途解除等の事前予告・理由開示
そのほか、フリーランスの行政機関への申告、その申告に対する不利益取り扱いの禁止、行政機関の報告徴収・立入検査、指導・助言、勧告・命令・公表、命令違反者への罰金(50万円以下)も規定されています。
<フリーランス法の対象となる取引など>
フリーランス法の対象となる取引は「業務委託」されています。
契約を定める民法の典型契約13類型にも業務委託契約自体の定めがありません。
したがって、契約の実質・実態や契約内容の性質などを総合的に考慮し、契約内容の確認、書類の準備や保存など現状把握と事前準備が必要です。
《 堅持 博 / 社会保険労務士・行政書士》